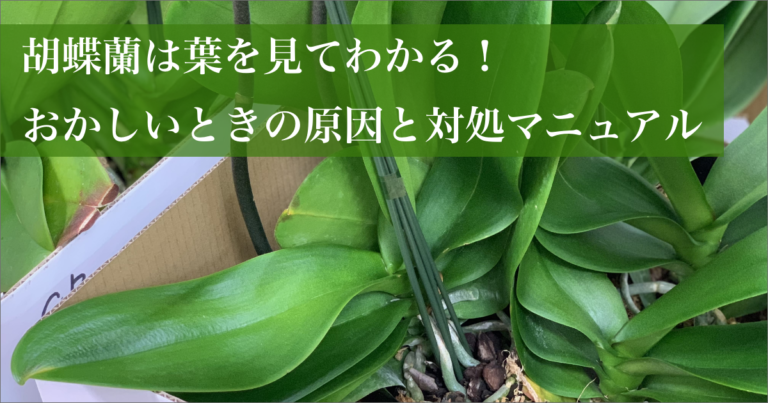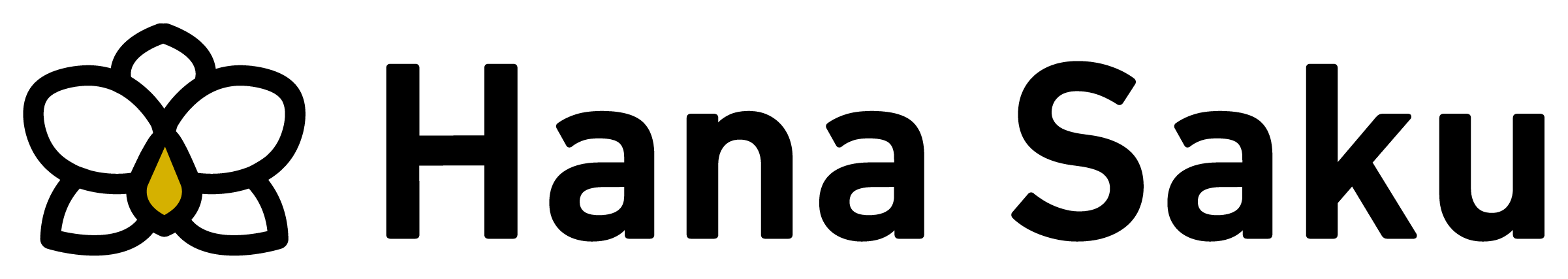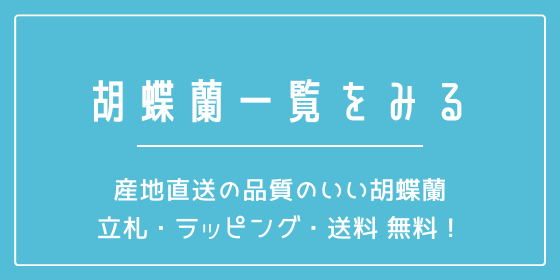
オリーブの特徴まとめ|目的別のおすすめ品種9選と選び方・育て方

オリーブは古くから世界中で栽培されている樹木です。たくさんの種類があり、観賞用としても楽しめるため、庭木やシンボルツリーとしても親しまれています。目的別に、家庭での栽培に適したオリーブの選び方や、おすすめの品種を紹介します。
オリーブの起源・由来

オリーブは丈夫で育てやすいため、世界中で栽培されています。暖かい場所を好みますが、耐寒性もあるので、幅広い地域で育てられているのです。
オリーブの果実は塩漬けやピクルスなどのほか、絞ってオイルにして食用にも使えます。貴重な食材として、古くから栽培が行われてきました。オリーブの歴史や、人類とのかかわりについて紹介します。
オリーブの栽培の起源はトルコやシリア
オリーブの原産地は西アジアや地中海沿岸一帯など、多岐にわたります。栽培の起源は古く、トルコやシリアなどの中東で約6,000年前に始まりました。中東から、ギリシャやイタリアに伝わったとされます。
オリーブは温暖な気候でよく育ち生命力が強いことから、幅広い地域に根付いていきました。各地に伝わるとともに、野生種にほかの品種を接ぎ木し、新しい品種が生み出されていったのです。
現代ではイタリアとスペインがオリーブの代表的な産地となっていて、世界で生産されているオリーブの半分以上のシェアを占めています。
神話にも登場する聖なる木
諸説ありますが、オリーブはギリシャ神話に登場する女神アテナのシンボルの木となっていて、神話ではアテナがつくり出したとされています。
旧約聖書の「創世記」の中で「ノアの方舟」のエピソードにも登場し、洪水の後でノアが世界の様子を探るために鳩を飛ばし、戻ってきた鳩がくわえていたものがオリーブの小枝です。
オリーブは生命力が強いため、復活の象徴とされたのでしょう。また、神話だけでなく「ハムラビ法典」の中にも、オリーブに関する記述が見つかっています。このことから、文明の発展にも影響を与えてきたことが分かります。
オリーブが日本に伝わったのは16世紀
日本にオリーブが伝わったのは16世紀で、キリスト教の宣教師が持ち込んだと伝えられています。当時は苗ではなく、樽に詰められたオリーブの実やオイルが持ち込まれました。
オリーブの苗木は江戸時代末期に海を渡ってきて、横須賀に植えられます。その後、神戸で栽培に成功し、実が採取されました。
明治期になると海産物をオイル漬けにして保存するために、オリーブオイルの本格的な生産が始められ、香川県の小豆島が日本のオリーブの産地となります。
岡山県瀬戸内市でもわずかに栽培されていますが、日本のオリーブの90%が小豆島で栽培されているのです。
オリーブの木の特徴

オリーブはモクセイ科の常緑高木(じょうりょくこうぼく)です。眺めているだけで南欧を思わせる雰囲気を味わえるため、洋風の庭木にも導入されています。
環境がよければ約10m程度の大きさになることもありますが、剪定で高さを抑えたり、樹形を整えたりする楽しみもある木です。オリーブの木の特徴を見ていきましょう。
オリーブの種類・品種
オリーブは世界中で栽培されているだけあって種類も多く、1,000種類以上の品種があります。日本の小豆島だけでも『60種類近い品種』が栽培されてきました。
オリーブは品種によって花の多さや葉の形に違いがあります。横に広がる樹形もあれば、縦にスッと伸びていく直立形もあり、それぞれに個性が異なるので、苗を購入する前にあらかじめどんな樹形に育つものなのかを押さえておくとよいでしょう。
剪定で樹形を整えることもあり、種類の違いを見分けることが難しいです。購入するときは、ネームタグをよく見て選びましょう。
たくさんのオイルを含む実が採れるものや受粉用に使われるものなど、種類によって育てられる目的が異なり、個性が豊かです。
細長く先のとがった葉が特徴
オリーブの木の魅力は多いですが、中でも葉の美しさが特徴的です。美しい葉の存在感が、シンボルツリーとして選ばれる理由の一つとなっています。
品種によってさまざまですが、葉の大きさは5~8cm程度です。葉の表側が緑色、裏側が緑灰色や銀白色となっています。
細長く先がとがった楕円形やへらのような形をしていて、葉の裏側に短い毛が生えています。常緑樹なので、年間を通じて美しい姿を楽しめるでしょう。
オリーブはどんな花や実をつけるの?
オリーブは5~6月頃に、白やクリーム色の小ぶりで可愛らしい花が咲きます。品種によって異なりますが、10~11月頃に実をつけます。それぞれに実の特徴が違い、大きな実をつけるものもあれば小さな実をつけるものもあり、形もさまざまです。
実ができると、緑色からだんだんと赤く熟していき、最終的には黒っぽい色に変化していきます。
「オリーブは必ず実がなるもの」と思っている人が多いかもしれませんが、自家結実性が弱いので、たくさんの実を採取するには『違う品種のオリーブを2種類以上植えること』が必要です。
花が咲く期間は1週間程度なので、受粉させるには『開花する時期が近いもの同士』を植えなければなりません。
目的別、オリーブの種類の選び方

オリーブはたくさんの種類があるので、どれを選んだらよいか分からなくなりがちです。「どこに植えるか」「何のために植えるか」など、目的別に選ぶとぴったりなものを選びやすいでしょう。
目的別に、オリーブの種類の選ぶときのポイントを紹介します。
庭のシンボルツリーにしたい
シンボルツリーはその家や庭の顔となる木です。オリーブは丈夫な上、剪定して好みの形にできるので庭木に向いています。
シンボルツリーとなるオリーブを探している場合、『枝葉や根がよく成長する品種』を選ぶことがおすすめです。縦によく伸びる直立形で、剪定しながらコンパクトに育てやすい品種を選ぶとよいでしょう。
庭のスペースに余裕がある場合なら、横に大きく枝を広げながら成長する品種でもOKです。横に広がるタイプは、ふんわりとした樹形に成長します。庭の広さを考慮しながら、好みの品種を選んではいかがでしょうか。
リビングのグリーンとして育てたい
オリーブは鉢植えでも育てられるため、リビングに置く観葉植物としてもおすすめです。
室内で観賞したい場合はコンテナに植え、日当たりがよい窓辺に置きましょう。ときどきはベランダや庭に出し、たくさんの日光をあててあげると元気に育ちます。
移動させることを考えると、『コンパクトに仕立てられる品種』がおすすめです。鉢植えでもよく育ちやすい「マンザニロ」や「チプレッシーノ」などを選ぶとよいでしょう。