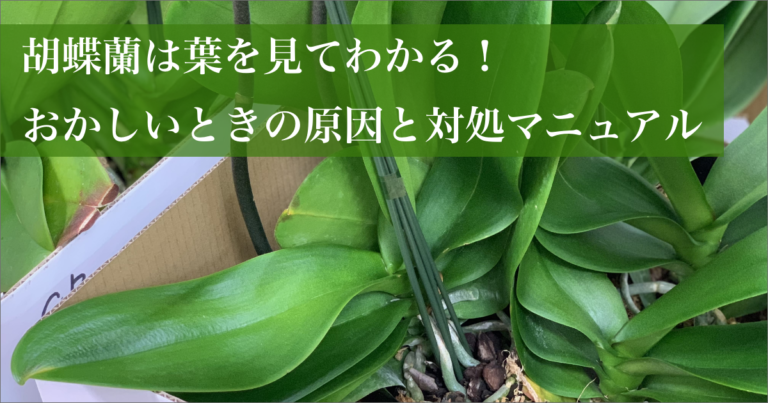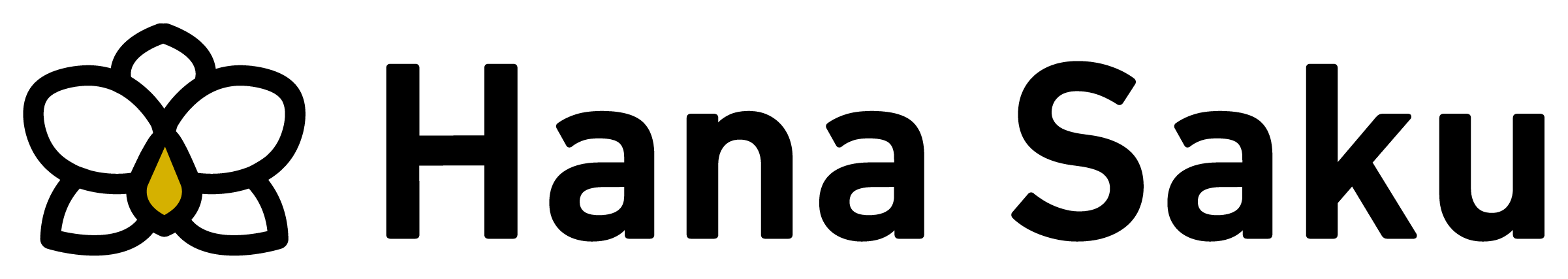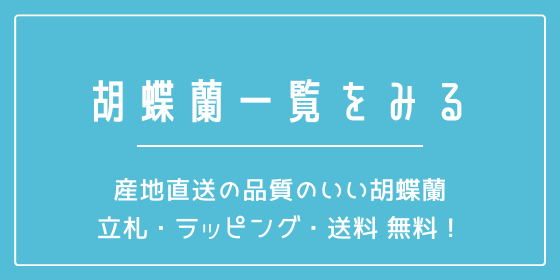
ラナンキュラスの育て方・栽培方法|手入れの仕方、上手に育てるコツ

重なり合う花弁が作り出す華やかな花姿が非常に魅力的なラナンキュラス。ガーデニンだけではなく、切り花のアレンジやプレゼントとしても人気があります。今回はそんなラナンキュラスの育て方について詳しく解説します。
ラナンキュラスを育てる前に知っておきたいこと

実際に育て始める前に、どんな花なのかを知ることは非常に重要です。ラナンキュラスの基本情報を以下の表にまとめてみました。
ラナンキュラスの基本情報
| 科・属名 | キンポウゲ科・キンポウゲ属 |
| 和名 | 花金鳳花(ハナキンポウゲ) |
| 英名 | Ranunculus, Persian buttercup |
| 学名 | Ranunculus asiatics |
| 花色 | 赤、白、ピンク、オレンジ、黄、紫など |
| 原産地 | ヨーロッパ東南部、中近東、西アジア、地中海沿岸 |
| 開花期 | 4~5月 |
ラナンキュラスの開花時期
キンポウゲ科・キンポウゲ属に分類されるラナンキュラスは、3月〜5月にかけて春に花を咲かせる球根植物です。秋から冬の間に球根を植えると、春には芽を出し、夏には茎・葉がすべて枯れて球根のまま休眠します。
以下の記事でラナンキュラスの見頃や季節について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
ラナンキュラスの種類と選び方

今では花色も豊富で、バラのような八重咲きが主流のラナンキュラスですが、ギリシャの原種は花びらが5枚の一重咲きで、花色が赤と黄の2色しか存在しなかったといわれています。ヨーロッパ周辺を中心に改良が行われ、現在では様々な咲き方・色・花の大きさの品種が流通しています。
では実際に、どのような花姿や色があるのか、多種多様な咲き方に焦点を当ててラナンキュラスの種類を簡単に紹介します。どんな種類が自分好みなのか、選ぶ際の参考にしてみてくださいね。
咲き方によって異なる種類
咲き方の種類とそれぞれの特徴を以下の表にまとめてみました。
| 咲き方 | 特徴 |
|---|---|
| 八重咲き | バラのような花姿 |
| 半八重咲き | 花芯が見える平咲き |
| 一重咲き | 花びらが5枚のみ |
| カール咲き | 花びらがカールしている |
| ピオニー咲き | 大きさの異なる花びらがフリル状に重なる |
| カメリア咲き | 八重ツバキのような花びらが特徴 |
| フリンジ咲き (カーネーション咲き) | 花びらの縁が波打つような花姿 |
以下の記事では、ラナンキュラスの種類についてさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
ラナンキュラスを育てる時に必要な準備

ラナンキュラスは、鉢植え・地植えのどちらの方法でも栽培が可能です。まずは、以下のものを準備しましょう。
- ラナンキュラスの苗/ 球根/ 種
- 土(鉢植えの場合は花用の培養土)
- 肥料(緩効性化成肥料)
- 支柱、紐
- 軍手
- スコップ
*鉢植えの場合は、植木鉢/プランター、鉢底ネット、鉢底石も用意 *地植えの場合は、有機石灰/ 苦土石灰も用意
適した土作りが重要
この準備段階で知っておくべきことは、適した土を用意することが、ラナンキュラスの栽培の成功につながるということです。具体的には、水はけのよい、弱酸性~弱アルカリ性の土壌を作ることが大切です。
鉢植えの場合は、市販の花用培養土を使うことをお勧めします。
地植えの場合は、植え付ける約1〜2週間前に苦土石灰(くどせっかい)を散布しましょう。これは、日本の土壌が酸性であることが多いため、アルカリ性を強める性質をもつ苦土石灰を中和させることで、ラナンキュラスに適した弱酸性~弱アルカリ性の土壌を作るためです。ただし、石灰の量が多すぎると土の質が悪化してしまうので十分注意しましょう。
鉢植え・地植え共に、元肥として緩効性化成肥料を足して、定期的に追肥を行いましょう。
ラナンキュラスの育て方

ラナンキュラスは、種・球根・苗から育てることが可能です。最も簡単に育てられるのはプランターで売られている苗で、その次に球根、種の順番で難易度が変わっていきます。草丈は基本的に30〜60cm程度で、鉢植え・地植えともにどちらの方法でも栽培が可能です。ここでは、
種からも育てられる?
先述の通り、ラナンキュラスは種からの栽培も可能です。しかし、初心者は苗や球根から育てることをお勧めします。ここでは、簡単に種からラナンキュラスを育てる方法を紹介します。
種まきの時期
ラナンキュラスが発芽する適温は15℃前後なので、地域によって異なりますが、9月中旬〜10月中旬頃に種をまきましょう。
種まきの方法
まず発芽を促すために、種を「吸水」させます。コットンやティッシュに水を含ませ、そこに種を挟み、冷蔵庫などの場所に約1日置いておくと良いでしょう。
「吸水」の作業を終えたら、育苗箱などに種をまきましょう。本葉が4〜5枚程ついてきたら、プランターや花壇などに植え替えを行います。
球根から育てる場合
球根の育て方について解説します。
球根の選び方
良い球根を選ぶことが、栽培の成功につながります。球根を選ぶ際は、重さがずっしりとあるか、皮にツヤがあるか、傷はないかどうかをしっかりと確認しましょう。
球根を植え付ける時期・方法
球根は10月頃に植え付けましょう。球根も、種と同じように「吸水」を行うことをお勧めします。この作業を怠ってしまうと、球根の場合は腐敗してしまう可能性があるので気をつけてください。寄植えや、他のラナンキュラスと一緒に植え付ける場合は、15cm程度の間隔を空けましょう。
苗から育てる場合
最も簡単な方法である、苗からの育て方について解説します。
苗の選び方
ラナンキュラスの苗が出回るのは、11月下旬から開花時期である4月頃にかけてです。その中でも春に出回っている苗の栽培がより簡単です。選ぶ際には、より大きくて多くの葉がついているか、株がしっかりとしているかを基準にしてみてください。
植え付け時期・方法
植え付け時期は、地域によって異なります。暖かい地域だと11月中旬~12月中旬、寒い地域の場合は10月上旬から11月中旬に植え付けます。実際に植え付ける際は、根鉢を崩さないようにすることがポイントです。
ラナンキュラスのお手入れ方法

ラナンキュラスを育てる際に気を付けるべき注意点や、育て方のコツを紹介します。しっかり確認して、綺麗なラナンキュラスを咲かせましょう。