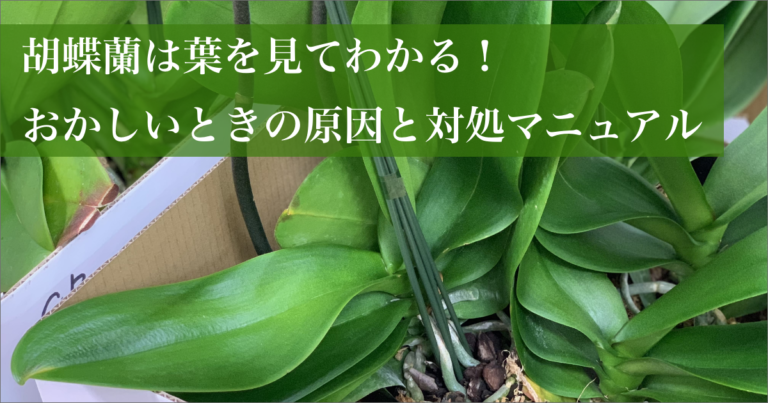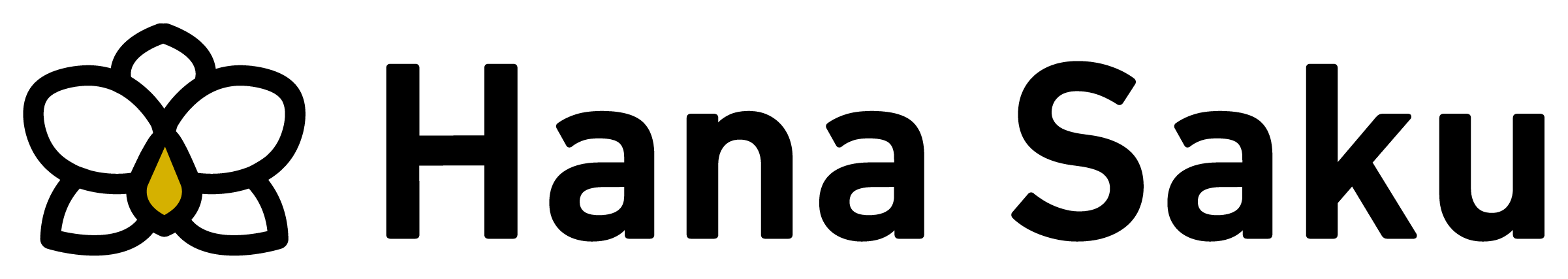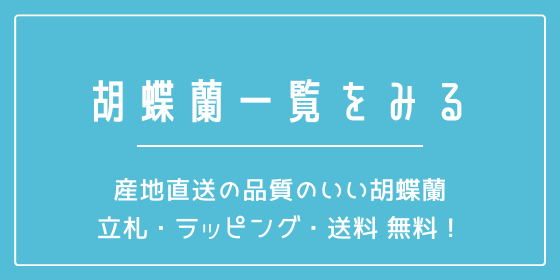
芍薬(シャクヤク)とは?特徴や花言葉・牡丹との違い・育て方・手入れ方法も解説

『芍薬(シャクヤク)』は、世界的に人気のある花で、さまざまな品種があります。自分好みの色や形を見つけて自宅で栽培してみませんか?きれいに咲かせるためのお手入れ方法を見ていきましょう。基本的な特徴や、よく似ている『牡丹』との違いも紹介します。
芍薬(シャクヤク)とはどんな花?

まずは、『芍薬(シャクヤク)』の特徴を紹介します。植物としての特徴や歴史について知り、理解を深めましょう。
芍薬(シャクヤク)の歴史や特徴
ボタン科ボタン属の『芍薬』は、草丈60~120cmほどの多年草の植物です。原産地は中国やモンゴルといった東アジアで、開花期は4~6月、5月中旬に見頃を迎えます。
開花期には『早朝に花が開き、夕方に閉じる』というのも特徴です。また、香水に使われるほど華やかな香りがあります。
名前に薬という文字が入っているのは、原産地である中国で紀元前から『薬草』として使われていたからです。日本へも、平安時代に薬草として伝わりました。
その後、花の美しさが注目され、鑑賞用の品種が作られたのです。しなやかで優しい姿を表す『綽約(しゃくやく)』という言葉が名前の由来ともいわれています。
芍薬(シャクヤク)の花の色や咲き方
美しい花が人気の芍薬にはさまざまな品種があり、咲き方のバリエーションが豊富です。愛好家が好みの花を咲かせるために、盛んに改良されてきました。
赤・白・ピンクなどのオーソドックスな色のほか、斑点やしま模様入りのタイプもあります。また、花は咲き方によって下記のように分類されています。
- 一重咲き:花びらが8枚程度
- 半八重咲き:花びらが8枚以上
- 金しべ咲き:雄しべが太く、金色に盛り上がる
- 扇咲き:雄しべが細長く、花びらとは異なる色をしている
- 冠咲き:雄しべが丸く盛り上がっている
- 手まり咲き:雄しべが花びらのようになり区別が付きにくい
- バラ咲き:全体がバラのような形
さまざまな咲き方があるため、自分好みの品種を見つけて栽培しましょう。
芍薬(シャクヤク)の花言葉
芍薬の花言葉は『恥じらい』『はにかみ』『謙遜』です。夕方に早々に花を閉じてしまう様子から、このような花言葉が付けられたといわれています。
また、『芍薬の花に、はにかみ屋の妖精が隠れていた』というイギリスの民話から作られたという説もあります。
英語には、『顔を真っ赤にする』という意味の『blush like a peony』という慣用句があります。peonyは芍薬のことです。恥じらっているときに顔が赤く染まる様子を表す言い回しにちなんだ花言葉とも考えられています。
芍薬(シャクヤク)と牡丹(ボタン)の違い

『peony』は、『芍薬』のほかに『牡丹』のことも意味します。英語圏では『芍薬』と『牡丹』は区別されていないのです。それほどまでに似ている二つの花には、どのような違いがあるのでしょうか?
違い①分類は木と草
まず挙げられる違いは、『木』と『草』という点です。『芍薬は草』に分類されます。冬になると地上部が枯れ、根だけが残り休眠状態に入るのです。
一方、『牡丹は木』に分類されます。茎が木質化していて、冬になっても地上部が枯れることはありません。秋に紅葉するのも両者の違いです。
また、芍薬の茎が真っすぐ伸びるのに対して、牡丹の茎は枝分かれしていきます。地面に近い場所で横ばいに育っていくのです。
違い②葉やつぼみ、匂いもチェックしよう
木と草という以外にも、芍薬と牡丹には違いがあります。
例えば、『芍薬の葉にツヤと丸みがある』のに対し、『牡丹はツヤがなくギザギザしている』のです。また、『つぼみが丸く蜜が出ているのが芍薬』で『とがっているのが牡丹』という違いもあります。
見た目で区別を付けにくいという場合には『香り』を確認してみましょう。芍薬はバラのように甘い芳香がありますが、牡丹にはありません。香水にも使われるほど華やかな香りのため、分かりやすい判断方法です。
芍薬(シャクヤク)の育て方ポイント

美しい花と芳しい香りが魅力的な芍薬は、自宅で育てることが可能です。栽培のポイントを押さえて、自分好みの芍薬を咲かせましょう。
芍薬(シャクヤク)に適した栽培環境
芍薬は、日当たりのよい場所か半日陰くらいの場所を好みますが、あまり暑さに強くはなく、涼しい地域の方が育てやすい植物です。根が太く葉も大きく茂るため、スペースを確保できる場所に植えましょう。
また、水はけがよく、栄養分が豊富な土を好みます。加えて、乾燥しないよう管理できる場所が向いています。
芍薬(シャクヤク)の水やりや肥料
鉢植えで育てる場合『水やりは土の表面が乾いたら』行います。水切れしないよう、よく観察して水やりすることが大切です。
地植えでは、水やりの必要はほとんどありません。ただし、長期間雨が降らず乾燥が厳しいときには、たっぷり水やりをしましょう。
また、栄養豊富な土壌でよく育つため、元肥も追肥もしっかり与えるのが正解です。不足すると花付きが悪くなる可能性があります。元肥には『緩効性化成肥料』を、追肥には『草花用化成肥料』を与えましょう。
追肥のタイミングは、早春の芽出し肥・花後のお礼肥・花芽ができる秋・冬の寒肥が有効です。
芍薬(シャクヤク)の植え付け・ 植え替え
根が込み合うと、花付きにも影響を与えてしまいます。そこで、鉢植えで育てている芍薬は『2~3年を目安に植え替え』をしましょう。根が育つスペースを確保するために、大きめの鉢を選ぶのがポイントです。
植え替えは『9~10月』に行います。このとき、元肥がしっかり配合された土を使うと、元気に育てやすいでしょう。
ただし、地植えした芍薬の植え替えは据え置きます。5~10年間はそのままで育てましょう。
芍薬(シャクヤク)の病害虫対策
病害虫の被害を受けることもあります。
例えば、アブラムシ・ヨトウムシ・ネコブセンチュウ・コウモリガなどの害虫の被害を受ける可能性があるのです。また、うどんこ病・灰色かび病・葉枯れ病なども病気のリスクもあります。