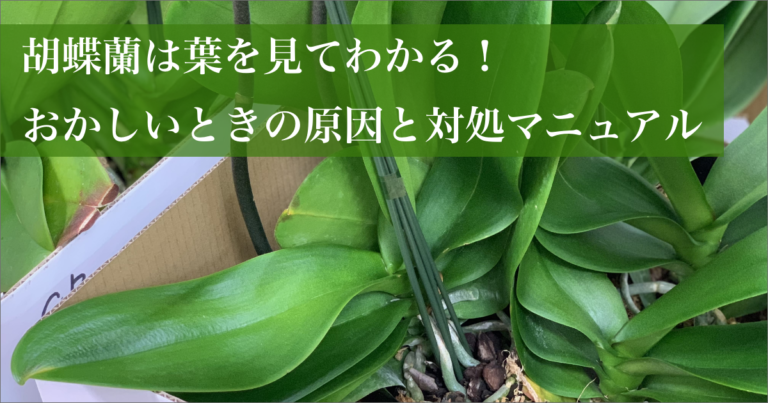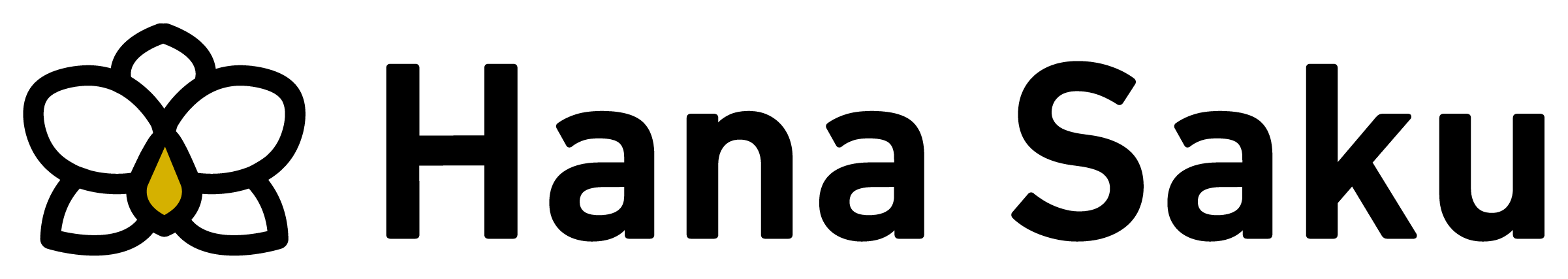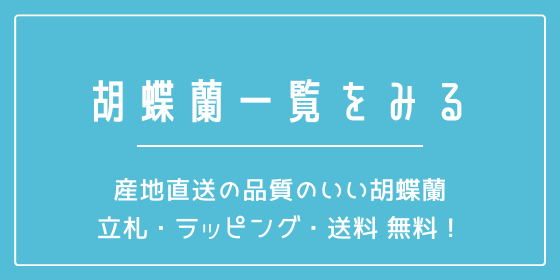
オミナエシ(女郎花)の花言葉の意味・由来|花の特徴なども紹介

夏から秋にかけて黄色い花を咲かせるオミナエシ。古来から日本人に親しまれてきたとされるこの植物には、一体どんな花言葉が存在するのでしょうか?花言葉の由来やオミナエシにまつわるその他豆知識も合わせて紹介します。
オミナエシ(女郎花)の花言葉の意味と由来

オミナエシにはどのような花言葉が存在するのでしょうか?由来なども合わせて紹介します。
オミナエシ全般の花言葉
オミナエシには「約束を守る」「美人」「はかない恋」「親切」などの花言葉が存在します。どの言葉も、オミナエシの繊細そうな見た目にぴったりの意味ですね。
オミナエシの花言葉の由来
それぞれの花言葉の由来を紹介します。
「約束を守る」
花言葉「約束を守る」は「おみなめし」という能の演目が由来であるとされています。
夫に浮気された妻が自害してしまい、後に彼女のお墓からオミナエシの花が咲いたという内容で、 夫の「二度と約束は破らない」という後悔の想いから「約束を守る」という花言葉が誕生したという説があります。
「美人」
花言葉「美人」は、この花の咲き姿に由来するといいます。細くてスラッとした茎に小さな花の数々を咲かせるオミナエシはまさにスタイルが良い美人さんのようですね。
「はかない恋」
花言葉「はかない恋」もこの花の咲き姿に由来します。風邪に揺られるかぼそいオミナエシの姿は、まさに寂しげに想い悩んでいるように見えます。
「親切」
オミナエシは万葉集が成立した奈良時代末期から「美人」の例えとして用いられ、当時の人々の理想的な女性像を表現する言葉の一つがこの「親切」だといわれています。
オミナエシ(女郎花)の花名(和名・英名・学名)と由来

オミナエシの和名・英名・学名にはそれぞれどのような由来が存在するのでしょうか?
オミナエシの花名(和名)とその由来
オミナエシは漢字で「女郎花」と表記され、この漢字に関係する由来がいくつかあります。ここでは、その中からいくつかを紹介します。
女性らしい印象から
オミナエシの女性らしい花姿に例えられたというこの説は、「オミナ」が女性を意味し、「エシ」は「へし(圧し)」という古語を意味することに由来します。他の女性を圧倒するほどの美しさという意味が込められています。
女飯という言葉から
黄色い粟飯(あわめし)を盛った女飯(オミナメシ)と、オミナエシの花が似ていることに由来して名付けられたという説です。
これには昔、男性が食べていたもち米で炊く白いご飯を男飯と呼んだことに対し、女性が食べていたのは黄色いアワのご飯で、この粟飯を女飯と呼んでいたという背景があります。
オミナエシの花名(英名)とその由来
オミナエシは英語で次のように呼ばれます。
- Golden lace
- Scabious patrinia
- Yellow patrinia
オミナエシの色の特徴を捉えた名前が多いですね。二つ目の「Scabious patrinia」は、学名からきています。
オミナエシの花名(学名)とその由来
学名は「Patrinia scabiosifolia」です。
オミナエシ(女郎花)は秋の七草の1つ

七草粥として食される「春の七草」。一方であまり知られていない「秋の七草」は目で見て楽しまれるものとされています。オミナエシはそんな「秋の七草」の一つです。ここでは、秋の七草について簡単に紹介します。
秋の七草
秋の七草を紹介します。
- 萩(ハギ)
- 桔梗(キキョウ)
- 葛(クズ)
- 藤袴(フジバカマ)
- 女郎花(オミナエシ)
- 尾花(オバナ ※ススキ)
- 撫子(ナデシコ)
秋の七草は美しさを観賞するためのものです。その起源は「万葉集」で詠まれたことにさかのぼるとされています。
奈良時代の貴族・歌人の山上憶良が詠んだこれら2首の歌。「朝貌」は、現在の「桔梗(ききょう)」のことを指すとされています。秋の七草は、観賞用としてしたしまれてきただけでなく、薬など実用的な草花として古来から日本人に重宝されてきました。
上記のリストの順番で、 「ハギ・キキョウ / クズ ・フジバカマ・オミナエシ / オバナ ナデシコ」 のように「5/ 7 / 5」のリズムに合わせて、是非覚えてみてください。