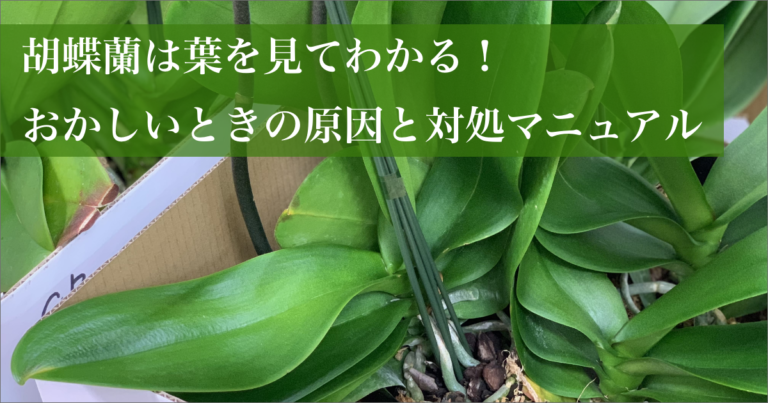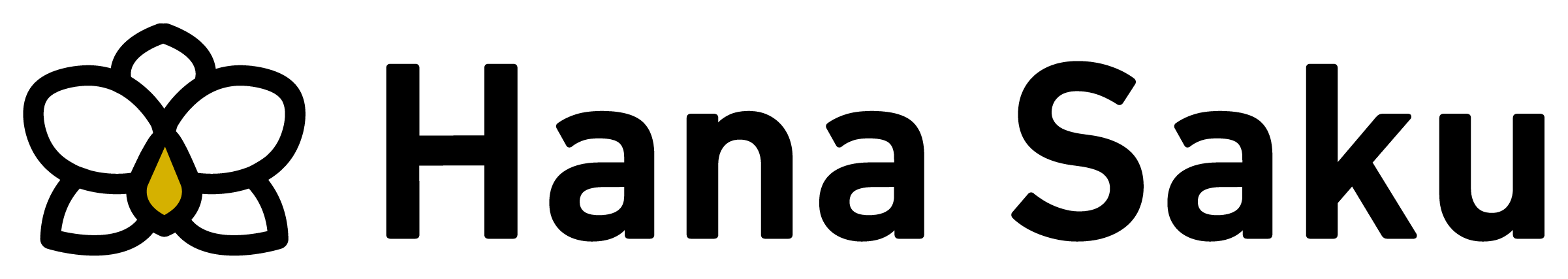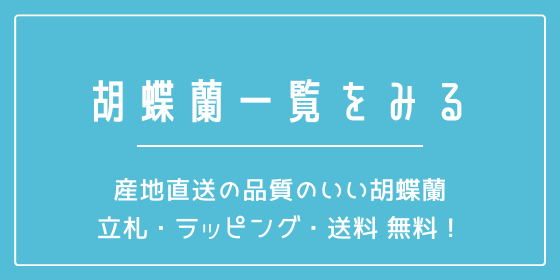
観葉植物の適切な水やり方法。季節別のタイミングなどをご紹介

観葉植物が枯れる原因は、水や日光が不足しているからとは限りません。水やりが多すぎて根腐れを起こすこともあります。季節別のタイミングや時間帯、葉水など、適切な水やり方法を確認しましょう。長期不在時の水やり方法についても解説します。
観葉植物の水やりの仕方
「植物には毎日水をあげなければならない」と思い込んではいませんか?観葉植物には季節ごとに適した水やりのタイミングがあります。
水やりをしても元気がないという場合は、以下のポイントを守っているかを確認してみましょう。
水やりの時間を決める
1日のうちで、水やりをする時間を決めましょう。暑くも寒くもない午前10時頃が目安ですが、住んでいる地域や季節ごとで時間を調節することも必要です。
たとえば、6~8月の真夏日は午前9時前か、強烈な西日が柔らかくなった18時以降がよいでしょう。
真夏日は太陽が照りつけている昼間に水を与えると、水がお湯になり植物がしおれやすくなります。一方、真冬は水が凍りやすいので、気温が下がる早朝や夕方を避けるのがベストでしょう。
観葉植物は温度の安定した室内で育てるため、それほど神経質になる必要はありませんが、『決まった時間』に与えれば、植物にストレスがかかりません。
『季節ごとの水のやり方』は後ほど詳しく説明します。
水の量はたっぷり受け皿に流れるくらい
水の量は、受け皿に溢れ出てくるくらいたっぷりと与えるのが基本です。
土全体に水が行き渡ることで、古い空気が押し出され新鮮な空気に入れ替わります。つまり、水やりは植物の根に『水と空気』が同時に与えられるのです。
水は葉や花にかけずにジョウロで根元部分に与えてください。受け皿にあふれた水はすぐに捨てましょう。
こちらの記事では水やりが楽しくなる、おしゃれなジョウロを紹介してみます。ジョウロをお探しの方はぜひチェックしてみてくださいね。
タイミングは土が乾いてから
観葉植物の水やりは、『土が完全に乾いてから』が原則です。もちろん、品種によって若干の差はありますが、ガーデニングのように毎日水を与える必要はありません。
特に、乾燥地帯が原産の多肉観葉植物は、水や茎にたっぷりと水を蓄えているため乾燥に強い傾向があります。その他の観葉植物も、やや乾かし気味で育てるとトラブルなく育つものが多いです。
土が乾いた状態とは

では『土が乾いた状態』とはどんな状態でしょうか?基本は見ためで判断しますが、それだけでは判断を誤る可能性もあります。土の状態を調べるいくつかの方法を紹介します。
土の色を観察して見極める
水やりの直後の土は黒く湿っています。水が蒸発し乾燥が進むにつれて色が薄くなり、黒→薄茶色→白と変化していくでしょう。触感もしっとりした土からパラパラしたものに変わっていきます。
しかし、表面の色が変わってきたからといって中まで乾燥しているとは限りません。日当たりのよい場所や空気が乾燥している状況下では、1日でも表面が乾いてしまうことがあるためです。
土の中の水分量をチェックする
土の中表面が白くなり、パラパラした状態になってきたら、土の中の水分量を確認してみましょう。
割りばしを深さ数cmのところまで挿し、土の付着具合を見てください。湿った黒い土が付着してこなかったら、土の中まで乾燥が進んでいる証拠です。
小型の植木鉢であれば、鉢を持ち上げてみましょう。湿っていると重く、乾燥すると軽くなります。
水やりタイミングがわかるグッズ
水やりのタイミングが分からないときは、市販されているグッズを使うのも手です。
土の中に挿し、色の変わり具合で水分量を判断するスティックタイプのものは、手を汚さず、且つ一瞬で判断が可能できるでしょう。
バーク・水苔・ハイドロカルチャーなど、どんなタイプの土にも使えるので、土いじりが好きな人は家に1つ用意しておくと便利です。
市販には、土の水分量を数値で表示するタイプも販売されているので、使いやすさや用途で選ぶとよいでしょう。
こちらの記事では電池なしで使える水分計『サスティー』をご紹介しています。一目で水やりのタイミングがわかる便利グッズですので、ぜひチェックしてみてください。
季節ごとの水やり方法

夏と冬では温度・湿度・日照時間などが異なるため、当然、土が乾くまでの時間も変わってきます。
また、季節によって植物の水の吸い上げ量が変化する点も考慮すべきでしょう。季節ごとの水やり方法のポイントを紹介します。
夏は乾燥と直射日光に注意
太陽の光が降り注ぐ夏は、風通しがよいベランダや窓際に観葉植物を出しておく人も多いですが、『乾燥』と『直射日光』には十分注意が必要です。
夏の暑い陽射しは、土の水分を急激に蒸発させます。加えて、生育期に入った植物はいつもよりも多くの水や養分を必要するため、土が乾燥しやすいのです。
植物がぐったりするほど土が乾燥している状態を『水切れ』といいます。水切れの兆候が見られたら、鉢ごとバケツに浸けて給水を行う、『腰水(底面給水)』を行いましょう。
ベランダに打ち水を行い、熱くなった地温を下げるのも有効です。
なお、日当たりのよい場所を好む観葉植物でも、夏の直射日光は苦手です。レースカーテンごしの明るい日陰に置くのが好ましいでしょう。
冬は水やりを控えめに
冬場は、植物が休眠期に入るため、水やりを控えめにするのが基本です。水を控える理由は主に2つあります。
1つは、休眠期の植物が吸収できる水の量は限られており、多すぎると逆に根腐れの原因になってしまうためです。冬は日差しも弱いため、土が乾くのにも時間がかかるでしょう。
もう1つは、植物は水やりを控えると『耐寒性』が増すためです。越冬のために、いつもより水やりの間隔を広げる方法を『ハードニング』といい、園芸店などでもよく用いられています。